第17回を迎えました,自作踏切シリーズ,今回のテーマは
モータードライバ基板のモジュール化
です.
具体的には何ぞやということなんですが,整備や組み込みを簡単にするために,
遮断機に使用しているステッピングモータを制御するためのIC
「TB6608FNG」に使うコンデンサや抵抗などの周辺部品を1つの基板に載せ,
arduinoとモータドライバをワンタッチで着脱できるようにしようという目論見です.
TB6608FNGをDIP変換基板にはんだづけ
TB6608FNGは,規格的に言うと「SSOP20」という規格らしいです.
詳しくはわからないのですが,ピン間隔が0.65mm幅で足が20ピンある物をこう呼んでいるみたいです.
正確な情報は,google先生のところへ,GO!
ということで,0.65mmピッチの部品に直接ケーブルをはんだづけするほどの技術もありませんので,0,65mmピッチをDIP基板用の
2.54mmピッチに変換してくれる基板があるので,それにTB6608FNGを取り付けていきましょう.
鉛筆の先っちょの部分とIC,変換基板の大きさを比較してみます.
いかにICが小さいかがお分かりいただけると思います.
これくらいでないと,お座敷に組み込めるようなメーカー既製品レベルのものが作れなかったんです.
「誰でも簡単に作れる」が目標とか言っておきながらすいません….
まずは変換基板にICを実装(はんだづけ)していきます.フラックス必須です.
位置をピッタリあわせたら..
端っこのピンだけはんだづけ
そしてフラックスを塗布して
はんだごての先に糸はんだをほんの少し乗せます.
これくらいで大丈夫.
いよいよピンのはんだづけです.
あまりICのピンにこて先が当たらないようにしながら,変換基板のパターンに塗るイメージでスライドさせます.
反対側も同様に.
この段階では,おそらくところどころにはんだブリッジができていると思います.
出来ていなければここで一旦作業終了です.
こんな感じでブリッジになっていたら,これを取り除いてあげなければなりません.
またフラックスをたっぷり塗布して,ブリッジのある場所にはんだごてをあてがいます.
そしてスッとはんだごてを引きます.
これで余分なはんだがこて先についてくるので,ブリッジが解消されます.
これで変換基板へのはんだづけは終了です
周辺部品のはんだづけ
ICを動作させるためには
- 220pFのコンデンサ1個
- 2Ωの抵抗器が二つ
- 電流制限用2.2KΩの抵抗器が1つ
がそれぞれ必要になります.
これを変換基板に取り付けてしまって,ICと周辺部品を一体化させたモジュールを作ろう!という作戦です.
では作っていきましょう.
こんな感じで配線する予定です.参考までにどうぞ.

次はこれにケーブルをつけてユニット化していきます.
ユニット化・完成
いよいよ最終段階です.ケーブルとコネクタ代わりのICソケットをつけていきます.
1番ピンと6番ピンが5Vピンを接続する端子なので,ここをVcc(+電源)からくるポリウレタン線でつなぎます.
この写真のようにICソケットをコネクタ替わりにしてarduinoと接続できるようにします.
これでユニット化完成です!
完成写真がコチラ

こんな感じで,一つのユニットとして組み込めるようになりました.
過去の踏切シリーズもぜひご覧ください.
→踏切
それでは,今回はこの辺で~👋




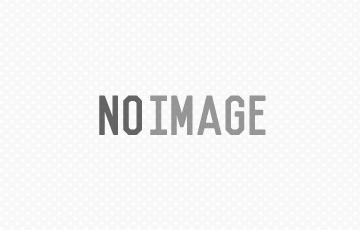




コメントを残す